- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して職場の健康保険などをやめた方
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
- 3ヶ月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の方
※ 国民健康保険は、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて国民健康保険税を納付しますが、世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)です。
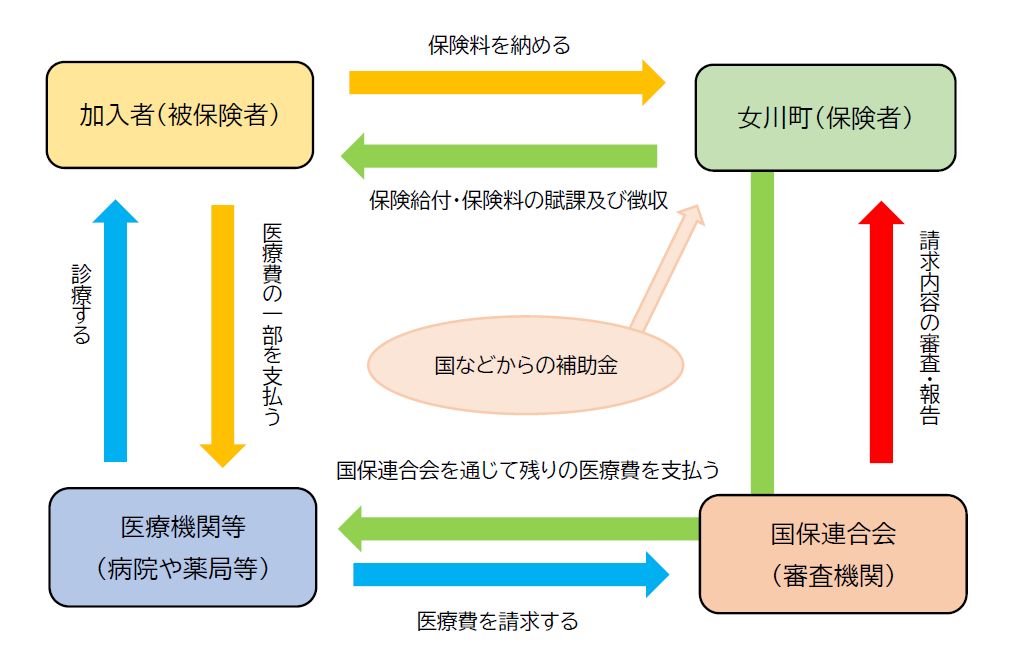
届出の際には、マイナンバーカードなどの身分証明書をお持ちください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険を辞めたとき | 職場の健康保険を辞めた証明書(資格喪失証明書等) |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった理由の証明書(資格喪失証明書等) |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止されたとき | 保護廃止決定通知書 |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村へ転出するとき | 資格確認書 |
| 職場の健康保険に加入するとき | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ(職場の資格確認書が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 死亡したとき | 死亡を証明するもの、資格確認書(※) |
| 生活保護が開始されたとき | 保護開始決定通知書、資格確認書(※) |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 町内で住所が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 修学のため、町外に住所を定めるとき | 在学証明書 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 資格確認書を破損したり、なくしたとき | 身分を証明するもの、破損した資格確認書等 国民健康保険資格確認書再交付申請書(PDF形式:88KB) |
| マイナ保険証をお持ちの方 | マイナンバーカード(利用には設定した4桁の暗証番号が必要です) |
|---|---|
| マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 |
| 病気とみなされないとき | 健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、美容整形正常な妊婦・出産など |
|---|---|
| 労災保険の対象となるとき | 仕事上での病気やけが |
| その他 | 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど |
| 所得区分 | 内容 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国民健康保険被保険者がいる場合が対象となります。ただし、70歳から74歳の国民健康保険被保険者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は収入383万円未満の国民健康保険被保険者については、申請により「一般」の区分となります。 |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の方 |
| 低所得者Ⅱ | 国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方 |
| 低所得者Ⅰ | 国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の方 |
申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
| 所得区分 | 世帯の基準総所得金額 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得区分 | 入院・世帯単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 4回目以降 | ||
| Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
| Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
| Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
| 一般 課税所得145万未満等 | 18,000円 ◎年間上限:144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ー |
| Ⅰ | 15,000円 | ー | ||
| 所得区分 | 入院日数 | 食費(1食) | |
|---|---|---|---|
| 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から※ | ||
| 住民税課税世帯の方 | 入院日数にかかわらず | 490円 | 510円 |
| 住民税非課税世帯の方 | 過去1年間の入院が90日以内 | 230円 | 240円 |
| 過去1年間の入院が91日以上 | 180円 | 190円 | |
| 住民税非課税世帯の方で 所得が一定基準に満たない 70歳以上75歳未満の方 (低所得Ⅰ) |
入院日数にかかわらず | 110円 | 110円 |
| 所得区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
|---|---|---|---|
| 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から※ | ||
| 下記以外の方 | 490円 (医療機関によって異なります) |
510円 (医療機関によって異なります) |
370円 |
| 住民税非課税世帯 | 230円 | 240円 | |
| 低所得者Ⅱ | |||
| 低所得者Ⅰ | 140円 | 140円 | |
急病などでマイナ保険証等を持たずに診療を受けたときや医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具費用がかかったときには、いったん全額自己負担となりますが、後日、申請して審査で決定(支給決定)されれば、自己負担分を除いた額が支給されます。
| 申請内容 | 申請に必要なもの | |
|---|---|---|
| 共通 | その他 | |
| やむを得ずマイナ保険証等を提示せずに診療を受けたとき | ・国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(対象者分) ・通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの) ・マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分) ・顔写真付きの身分証明書 |
・領収書(原本) ・診療報酬明細書 |
| 医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具を購入したとき | ・領収書(原本) ・医師の診断書 |
|
| 医師の指示、同意により、はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき。 | 本人やご家族が手続きをする場合は、以下をお持ちください。 ・はり・きゅう・マッサージの領収書 ・医師の同意書または診断書 ・施術明細書(内容の分かるもの) |
|
| 海外で診療を受けたとき(診療目的の渡航の場合は除く) | ・領収書(原本) ・診療を受けた方のパスポート ・診療内容明細書(外国語作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります。) ・領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります。) |
|
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者(加害者)の行為により病気・ケガをして、国民健康保険で治療を受けようとする場合は必ず届け出をお願いします。このような治療に要する医療費は、原則 加害者の負担となりますが、国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合は、国民健康保険が一時的に医療費を立て替えるものであり、その後に加害者に医療費を請求することになります。加害者から事故の治療費用を受け取って示談をしてしまうと、国民健康保険で治療を受けられなくなります。示談をする場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
届出様式は下記の宮城県国民健康保険団体連合会ホームページより、ダウンロードして使用してください。
| 送付された通知書、資格確認書またはマイナ保険証、医療機関等の領収書、世帯主の通帳、世帯主および受診者のマイナンバーがわかるもの(届出人が異なる場合は、届出人分も) |
国民健康保険高額療養費の支給申請は、これまで該当する度に申請が必要でしたが、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書で口座登録していただくと2回目以降は申請不要となり、原則として自動振込となります。
対象となる方には、高額療養費支給申請のお知らせの際に簡素化申請書を同封しますので、必要事項を記入し、以下の書類を持参のうえ申請してください。
| 資格確認書またはマイナ保険証、世帯主の通帳、世帯主および受診者のマイナンバーがわかるもの、来庁者の身分証明書 |
| 所得区分 | 世帯の基準総所得金額 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得区分 | 入院・世帯単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 4回目以降 | ||
| 現役並み 所得者 |
Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
| Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
| 一般 課税所得145万未満等 | 18,000円 ◎年間上限:144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ー |
| Ⅰ | 15,000円 | ー | ||
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 212万円 |
| イ | 基礎控除後の所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| ウ | 基礎控除後の所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 60万円 |
| オ | 住民税非課税 | 34万円 |
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | Ⅲ 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| Ⅱ 課税所得380万円以上 | 141万円 | |
| Ⅰ 課税所得145万円以上 | 67万円 | |
| 一般 課税所得145万円未満等 | 56万円 | |
| Ⅱ 住民税非課税世帯 | 31万円 | |
| Ⅰ 住民税非課税世帯 | 19万円 | |
出生児1人につき 一律50万円
| 出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、同制度対象である旨のスタンプが押印されているもの)、世帯主の通帳、母子手帳、世帯主および分娩者のマイナンバーが分かるもの、(直接支払制度を利用した方は)直接支払制度合意文書の写し |
| 葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状など)、葬祭を行った方の通帳、葬祭を行った方・世帯主および亡くなった方のマイナンバーが分かるもの |
医療機関でのマイナンバーカードを利用した受診方法は以下のとおりです。
従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を送付します。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまでと変わらない窓口負担で医療を受けることができます。
令和6年12月2日以降はマイナ保険証を利用することが基本となりますのでぜひご利用ください。
また、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等にご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障がいのある方など)や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方は、申請をしていただくことで、「資格確認書」の交付を受けられます。
世帯主及び申請者のマイナンバーが分かるもの、来庁者の身分証明書
申請に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
女川町国民健康保険の被保険者でマイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望される方は、申請により利用登録を解除することができます。
よくある質問をQA方式で掲載しておりますのでご覧ください。
©Onagawa Town. All rights reaserved.